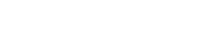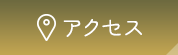胃炎とは
 胃炎は、胃の内側にある粘膜に炎症が起きた状態です。発症の仕方により「急性胃炎」と「慢性胃炎」に分けられます。原因は様々で、食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレスなどの生活習慣によるものから、ピロリ菌感染によるものまで様々です。
胃炎は、胃の内側にある粘膜に炎症が起きた状態です。発症の仕方により「急性胃炎」と「慢性胃炎」に分けられます。原因は様々で、食べ過ぎ、飲み過ぎ、ストレスなどの生活習慣によるものから、ピロリ菌感染によるものまで様々です。
適切な治療を行えば多くの場合は改善しますが、慢性胃炎を放置すると胃潰瘍や胃がんのリスクが高まる可能性があるため、早めの治療が大切です。
急性胃炎
突然発症する胃炎で、多くの場合は胃を休ませることで自然に改善します。症状が強い場合は、点滴や胃薬による治療を行います。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)
主にピロリ菌感染により、長期間かけて徐々に胃の粘膜が傷つけられる状態です。進行すると正常な胃粘膜への回復が難しくなり、胃がんのリスクも高まります。
急性胃炎と慢性胃炎の違い
急性胃炎は、短期間で突然発症する胃の炎症で、暴飲暴食、ストレス、薬の影響などが原因となります。症状としては、胃の痛み、吐き気、嘔吐などがみられますが、適切な治療により比較的早く回復します。
一方、慢性胃炎は長期間にわたり続く胃の炎症で、ピロリ菌感染や過度の飲酒、刺激物の摂取などが関与します。自覚症状が少ない場合もありますが、進行すると胃もたれや食欲不振が現れることがあります。
胃炎の症状
胃炎の症状には、むかつき、胸やけ、胃の痛み、吐き気などが代表的です。ただし、これらの症状は胃がんなど他の重大な胃の病気でも現れることがあるため、症状が続く場合は医師による診察を受けることが大切です。
急性胃炎の症状
急激に以下のような症状が現れます。
- 胃やみぞおちの痛み
- むかつきや吐き気
- 胸やけ
- お腹の張り
- 食欲不振
重症の場合は吐血や下血を伴うことがあります。
慢性胃炎の症状
以下のような症状が繰り返し現れます。
- 食事の前の胸やけ
- 食後の胃もたれ
- みぞおちの痛み
- 食欲不振
ただし、症状がないまま進行することもあるため、定期的な検査が重要です。
胃炎の原因
急性胃炎の原因
不適切な食生活
 暴飲暴食や刺激物の摂り過ぎにより、胃酸が過剰に分泌され、胃の粘膜に炎症が起こります。喫煙も胃の血流を悪くし、胃炎を引き起こす原因となります。
暴飲暴食や刺激物の摂り過ぎにより、胃酸が過剰に分泌され、胃の粘膜に炎症が起こります。喫煙も胃の血流を悪くし、胃炎を引き起こす原因となります。
生活習慣の乱れ
 ストレス、睡眠不足、不規則な生活により自律神経のバランスが崩れ、胃の機能低下や胃酸の過剰分泌を引き起こします。
ストレス、睡眠不足、不規則な生活により自律神経のバランスが崩れ、胃の機能低下や胃酸の過剰分泌を引き起こします。
慢性胃炎の原因
大部分はピロリ菌感染が原因です。ピロリ菌が胃の粘膜を傷つけ、慢性的な炎症を引き起こします。
萎縮性胃炎の原因
慢性胃炎が長期間続くことで、胃の粘膜が薄くなった状態です。進行すると胃の粘膜が腸の粘膜のような状態(腸上皮化生)になり、胃がんのリスクが高まるため、定期的な検査による経過観察が必要です。
急性胃炎はうつる?
 急性胃炎自体は感染症ではないため、人から人へ直接うつることはありません。
急性胃炎自体は感染症ではないため、人から人へ直接うつることはありません。
しかし、原因によっては注意が必要です。例えば、ウイルスや細菌感染による胃炎の場合、嘔吐物や便を介して感染することがあります。特にノロウイルスやロタウイルスなどが原因の場合は、手洗いや消毒を徹底し、感染予防を心がけることが大切です。
胃炎の検査
 胃炎の診断では、まず詳しい問診により症状や生活習慣をおうかがいします。ピロリ菌感染の有無や胃の粘膜の状態を調べるため、主に胃カメラ検査を行います。特に慢性胃炎の場合は、胃がんのリスクを早期に発見するためにも、定期的な検査が重要です。
胃炎の診断では、まず詳しい問診により症状や生活習慣をおうかがいします。ピロリ菌感染の有無や胃の粘膜の状態を調べるため、主に胃カメラ検査を行います。特に慢性胃炎の場合は、胃がんのリスクを早期に発見するためにも、定期的な検査が重要です。
急性胃炎の治療
症状の経過や食事内容、服用中の薬などについて詳しくおうかがいし、適切な治療方針を決定します。必要に応じて胃カメラ検査を行い、胃の粘膜の状態を直接確認します。重大な病気が隠れていないかの確認も含め、正確な診断を行います。
慢性胃炎の治療
胃カメラ検査で胃の粘膜の状態を詳しく観察し、ピロリ菌感染の有無を確認します。ピロリ菌が見つかった場合は除菌治療を行います。また、胃の粘膜が薄くなる萎縮性胃炎や、さらに進行した腸上皮化生は胃がんのリスクが高まるため、早期発見・早期治療が大切です。
胃炎の食事
急性胃炎の食事
症状が強い時は胃を休めるため、白湯や番茶程度の摂取にとどめます。症状が落ち着いてきたら、おかゆなどの消化の良い食事から徐々に始めます。
回復後も以下の点に注意が必要です。
- 暴飲暴食を避ける
- 脂っこい食事や刺激物を控える
- 就寝の2~3時間前までに夕食を済ませる
慢性胃炎の食事
急性胃炎ほどの食事制限は必要ありませんが、以下の点に気をつけましょう。
- 消化の悪い食事(ラーメン、脂っこい食事など)は控えめに
- ゆっくりよく噛んで食べる
- バランスの良い食事を心がける
- 規則正しい食事時間を保つ