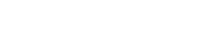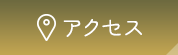腸炎とは

腸炎は、様々な原因で腸に炎症が起こる病気の総称です。主な症状として、下痢、腹痛、発熱、嘔吐などが見られます。原因により、感染性腸炎と非感染性腸炎に大きく分けられます。
感染性腸炎
ウイルスや細菌、時には寄生虫による感染で起こる腸炎です。主な原因として以下のようなものが挙げられます。
- ウイルス:ノロウイルス、ロタウイルスなど
- 細菌:サルモネラ菌、病原性大腸菌、カンピロバクターなど
非感染性腸炎
感染以外の原因で起こる腸炎です。主な原因として以下のようなものが挙げられます。
- 食べ過ぎや飲み過ぎ
- 消化不良
- 食物アレルギー
- 虚血性腸炎(腸の血流低下による炎症)
- 憩室炎(腸の壁にできたくぼみの炎症)
虚血性大腸炎
虚血性大腸炎は、大腸の血流が一時的に不足し、腸の粘膜がダメージを受けて炎症や潰瘍が生じる病気です。比較的高齢者に多く、左側の大腸(特にS状結腸)に発生しやすいとされています。
症状
- 突然の腹痛(特に左下腹部)
- 下血・血便(鮮血または暗赤色の血)
- 軽度の下痢を伴うことがある
- 吐き気や発熱(重症例)
原因
- 動脈硬化(加齢・高血圧・糖尿病などの影響)
- 便秘による腸管圧の上昇
- 脱水や低血圧による血流低下
- 血管の異常(血栓・動脈塞栓症など)
急性腸炎
急性腸炎は、腸内に感染が起こり、炎症を引き起こす疾患です。主にウイルスや細菌が原因となり、食中毒や感染症として発症することが多いです。
症状
- 下痢(水様性や血性の便)
- 腹痛(強い痛みを伴うことも)
- 発熱(特に細菌感染の場合)
- 吐き気・嘔吐(ウイルス感染時に多い)
- 倦怠感・脱水症状
原因
- ウイルス感染(ノロウイルス・ロタウイルスなど)
- 細菌感染(サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌・カンピロバクターなど)
- 寄生虫感染(アメーバ赤痢など)
- 食中毒(汚染された食品・飲料)
憩室炎
憩室炎は、大腸の壁にできた袋状のくぼみ(憩室)に炎症が起こる病気です。日本では特に右側結腸(盲腸・上行結腸)にできやすいのが特徴ですが、欧米では左側のS状結腸に多くみられます。
症状
- 下腹部痛(特に右下腹部・左下腹部)
- 発熱(38℃以上のことも)
- 便秘または下痢
- 吐き気・食欲低下
- 血便(重症例では出血を伴うことも)
原因
- 便秘による腸内圧の上昇
- 食生活(低食物繊維・高脂肪の食事)
- 加齢(腸の壁が弱くなりやすい)
- 免疫力の低下
- 細菌感染(憩室内に便が溜まり炎症を引き起こす)
腸炎の検査
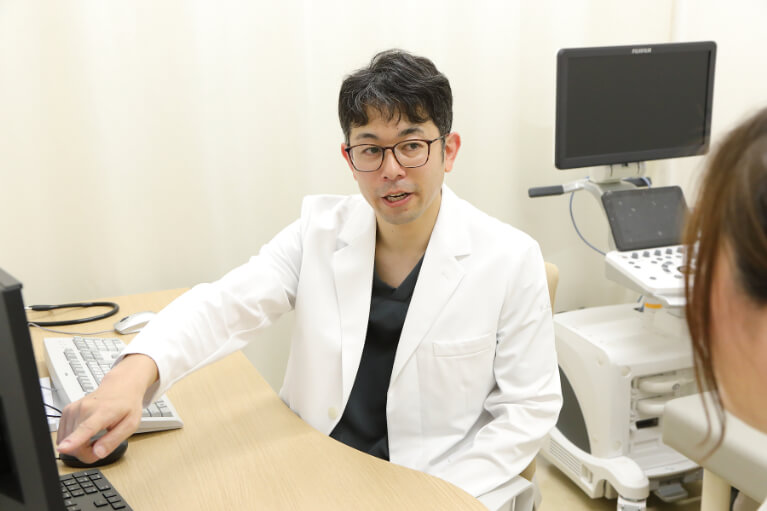
腸炎の診断には、問診、身体診察、血液検査、便検査、画像検査(CT、腹部超音波検査、内視鏡検査など)など、様々な検査が行われます。
問診
- 症状、発症時期、経過、既往歴、服薬歴などを詳しくお伺いします。
- 特に、腹痛の部位、性状、持続時間、血便の有無、便通の状態などを確認します。
身体診察
- 腹部の聴診、触診を行い、腸の音や圧痛の有無などを確認します。
- 発熱、脱水症状の有無なども確認します。
血液検査
- 炎症反応(白血球数、CRPなど)や貧血の有無を確認します。
- 肝機能、腎機能なども評価します。
便検査
- 細菌やウイルス感染の有無を確認します。
- 潜血反応の有無も確認します。
画像検査
CT検査
- 腹部の炎症や合併症(穿孔、膿瘍など)の有無を確認します。
- 虚血性大腸炎では、腸管の壁肥厚や血流低下などが認められることがあります。
- 憩室炎では、憩室の炎症や周囲組織への炎症の広がりを確認します。
腹部超音波検査
- CT検査と同様に、腹部の炎症や合併症の有無を確認します。
- CT検査よりも簡便に行える場合があります。
内視鏡検査(大腸カメラ)
- 腸管内の粘膜の状態を直接観察します。
- 組織採取(生検)を行い、病理検査を行うこともあります。
- 虚血性大腸炎では、粘膜の浮腫、発赤、潰瘍などが認められることがあります。
- 憩室炎では、憩室の炎症や出血を確認します。
虚血性大腸炎の治療
多くの場合、腸を休ませる保存的な治療で改善します。治療の内容は症状の程度によって異なります。
軽症の場合
- 食事制限による腸の安静
- 水分補給
- 段階的な食事の再開
重症の場合
- 入院による治療(絶食、点滴)
- 必要に応じて抗生剤の使用
- 症状が落ち着いてから段階的に食事を開始
通常1~2週間程度で改善しますが、4人に1人程度で再発することがあります。まれに腸管の狭窄や出血などの合併症が起きた場合は手術が必要となることもあります。
急性腸炎の治療
急性腸炎の治療は、原因と症状の程度によって異なります。
水分・電解質の補給
- 脱水予防が最も重要
- 経口補水液やスポーツドリンクを少しずつ摂取
- 嘔吐が強い場合は点滴による補給
薬物療法
- 吐き気が強い場合は吐き気止めを使用
- 腸内環境を整えるため整腸剤を使用
- 細菌が原因の場合は必要に応じて抗生剤を使用
- 下痢止めは原則使用しない(感染を遷延させる可能性があるため)
食事療法
症状が改善してきたら、以下の順で食事を再開します。
- うどんやおかゆなどの消化の良いもの
- バナナなどの軽い食べ物
- 乳製品や脂っこい食事は避ける
憩室炎の治療
症状の程度によって治療方針が異なります。
軽症の場合
- 自宅での安静が基本
- 数日間は水分やスープ中心の食事
- 徐々に消化しやすい食事に移行
- 必要に応じて痛み止めや抗生剤を使用
重症の場合
- 入院による治療
- 点滴による水分補給
- 抗生剤の投与
- 症状改善まで絶食
- 膿瘍がある場合は排膿処置
- 腸管破裂や腹膜炎の場合は手術が必要
治療後は再発予防のため、食事内容の見直しや便秘の予防が重要です。
腸炎の食事
腸炎(虚血性大腸炎、急性腸炎、憩室炎)の食事療法は、病状の回復を助け、再発を予防するために非常に重要です。
食事のポイント
急性期
腸管を安静にするため、絶食または消化の良い流動食にします。脱水症状がある場合は、水分補給(経口補水液など)を十分に行います。
食事の例
- 重湯
- おかゆ
- スープ
- ゼリー
- 経口補水液
回復期
徐々に消化しやすい食事に切り替えていきます。刺激物(香辛料、アルコール、カフェインなど)や食物繊維の多いもの、脂っこいものは避けましょう。調理法は、煮る、蒸すなど、油を控えたものがおすすめです。
食事の例
- 軟飯
- うどん
- 鶏ひき肉の煮物
- 豆腐
- 白身魚
- 野菜の煮物(柔らかく煮たもの)
- バナナ
- りんご
慢性期
バランスの取れた食事を心がけ、規則正しい食生活を送ります。便秘にならないように、水分や食物繊維を適切に摂取します。ただし、憩室炎の場合は、食物繊維の摂取量に注意が必要です。
食事の例

- バランスの取れた食事(主食、主菜、副菜を組み合わせる)
- 主食:ご飯、パン、麺類
- 主菜:魚、肉、卵、大豆製品
- 副菜:野菜、きのこ、海藻類
疾患別の注意点
虚血性大腸炎
- 動脈硬化の原因となる高脂肪食、高コレステロール食は避けましょう。
- 便秘を予防するために、水分や食物繊維を適切に摂取しましょう。
急性腸炎
- 原因が特定できている場合は、原因食品を避けましょう。
- 下痢が続く場合は、脱水症状に注意し、水分補給を十分に行いましょう。
憩室炎
- 急性期は、腸管を安静にするため、絶食または流動食にします。
- 回復期以降は、食物繊維の多いもの(野菜、果物、豆類など)や、種実類(ナッツ類、ごまなど)は、憩室を刺激する可能性があるため、摂取を控えめにするか、細かく刻んで調理しましょう。
- 便秘を予防することが重要です。